【江戸崎城】
江戸崎城は江戸崎氏(江戸崎土岐氏、土岐原氏)の
居城として知られています。
嘉慶元年(1387年)、
美濃(岐阜県)出身の土岐原氏が、
室町幕府の重職である関東管領上杉氏の求めにより、
「信太庄惣政所(しだのしょうそうまんどころ)
=直接土地に根付いて統治する職務者」
としてこの地に 入り、江戸崎城を築きました。
土岐系図には、土岐原景秀(ときはらかげひで)が
江戸崎城を修築したと記されてるとのことです。
築城年は室町時代、永享11年(1439年)です。
その後、景成(かげなり)、治頼(はるより)、
治英(はるひで)、治綱(はるつな)と
常陸土岐氏である土岐原氏5代の居城となります。
なお、治頼の兄には
戦国時代の美濃国の守護大名であった
土岐頼武および土岐頼芸がいます。
土岐原氏は、稲敷地方一帯を
約200年間にわたり統治し、
江戸崎まちなか地区の原型を作りました。
なお土岐原氏の傍流には、
甲斐国武田氏に仕え陣馬奉行として
活躍した原昌俊・昌胤父子や、
織田信長や豊臣秀吉に仕えた原長頼などがいます。
戦国時代に入り、
小田氏などと争っていましたが、
天正18年(1590年)、
豊臣秀吉の小田原征伐の際、
豊臣方に参じた佐竹義宣の実弟である
蘆名義広の攻撃により
江戸崎城は落城し土岐原氏は滅亡しました。
スポンサーリンク
その後、佐竹義重の二男で
佐竹義宣の実弟、蘆名盛重(蘆名義広)が
4万5千石の領主として入城しました。
蘆名盛重は城下の不動院に、
蘆名一門の出とされる
随風(のちの天海)を迎えており、
後に天海は徳川家康の知遇を得て
江戸幕府にて重用されることとなるのでした。
慶長5年(1600年)の
関ヶ原の戦いで佐竹義宣は
上杉景勝とともに西軍である
石田三成方についたことから、
敗戦後の慶長7年(1602年)、
徳川家康によって佐竹氏は
出羽秋田藩に減移封処分となり、
蘆名氏もそれに追従して
秋田・角館へ去ることになります。
その後江戸崎城は廃城となりました。
現在城址には町民研修センター、
江戸崎小学校があります。
小学校南側の城山稲荷の周辺が
本丸跡で土塁が残っています。
慶長8年(1603年)に
本多正信や内藤清成らと並んで
関東総奉行を務めた
徳川氏譜代の家臣・
江戸幕府町奉行青山忠成(あおやま ただなり)が
常陸江戸崎1万5千石の所領を得て入封し、
江戸崎藩が立藩されます。
青山忠成の嫡子・青山忠俊は
父と別に5千石を領していましたが、
徳川家光の後見人となったため、
慶長15年(1610年)に
下野国都賀郡鹿沼において5千石を加増され、
独立した1万石の大名となっています。
慶長18年(1613年)、
青山忠成が死去したため、
青山忠俊がその遺領を相続して
3万5000石を領することとなりました。
元和2年(1616年)には老中に栄進し、
元和6年(1620年)には
1万石を加増の上で
武蔵岩槻藩に加増移封となりました。
その後、常陸古渡藩より
丹羽長重が2万石で入封します。
けれども元和8年(1622年)に
3万石加増の上で陸奥棚倉藩へ
加増移封となり、江戸崎藩は廃藩となったのでした。
スポンサーリンク
【目印】
江戸崎小学校手前100m左を車で行けます。
【縄張形態】
平山城(崖端城)
【標高(比高)】
20m(15m)
【築城主】
土岐秀成か?
【築城年】
南北朝時代か?
【廃城年】
慶長7年(1603年)
【主な城主】
江戸崎氏、蘆名盛重
【遺構】
曲輪、土塁
【交通アクセス】
(車)
圏央道「稲敷」ICから10分程度
奥に駐車スペース
【所在地】
〒300-0500 茨城県稲敷市江戸崎甲3211
土岐頼武・土岐頼純VS土岐頼芸~美濃守護土岐氏~度重なる家督争いで衰退し、斎藤道三に乗っ取られる!
木原城~土岐氏の家臣であった近藤氏の居城と伝えられており、城主の近藤利勝の肖像画が発見されました。
古渡城(常陸国)~築城は山岡景友、後に丹羽長重が大名再スタートとなった城です。
万喜城~築城は上総土岐氏と伝えられており、本多忠勝が一時居城していました。
小田城跡(つくば市)~鎌倉初期に八田知家が築城し、戦国時代の小田氏15代の居城でした。
藤沢城~小田城主の小田氏の支城であり、小田城を奪われた際には何度も拠点とした城です。
関城跡(常陸国)~南北朝時代に南朝方であった関宗祐・宗政親子が北朝の標的に晒されながらも戦いました。
大宝城(茨城県)~関東最古の八幡宮である大宝八幡宮境内にあり下妻氏によって築城された城です。
土浦城~伝説上では平将門の砦、文献上では八田知家後裔の若泉氏が築城、戦国期を経て土浦藩となる。
阿波崎城~南北朝時代に南朝方の北畠親房が転戦した古城跡です。
神宮寺城(常陸国)~南北朝時代に築城された南朝方の城で遺構が良好な状態で残っています。
鹿島城(常陸国)~平安時代末期に鹿島氏によって築城されました。築城者の平姓鹿島氏とは?
塚原城~大掾氏一族で鹿島氏分流の塚原氏が居城し、剣聖として有名な塚原卜伝も城主となりました。
島崎城~常陸大掾氏の一族である島崎氏の居城、よく整備され遺構もわかりやすく登城しやすい城です。
常陸・長山城~大掾氏の庶流行方氏の一族の長山氏が居城し、同族の島崎氏に攻められました。
平将門公本據豊田館跡~平将門誕生の地と伝わる場所、後に豊田氏の向石毛(向石下)城址となりました。






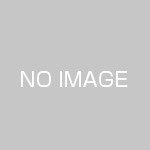









この記事へのコメントはありません。