【藤倉舘】
(ふじくらたて)
藤倉館跡。
【形態】
平城
【築城年】
建久3年(1192年)
【築城者】
藤倉盛義
【遺構】
土塁、空堀、堀
藤倉舘は、建久3年(1192年)に
会津の守護であった
佐原義連の孫であり、
佐原盛蓮の三男である
藤倉盛義が築いて居館としたと伝えられています。
藤倉氏は建長4年(1252年)、
藤倉盛弘の時、
金上館へ移封され
金上氏を名乗ったと伝えられていますが、
詳しいことはわかってはいません。
館は方形居館で周囲に土塁と濠があり、
現在でもはっきりと確認できます。
南には虎口があります。
東側には庭園があったとのことです。
<庭園について>
なお、案内板には「遠州流」と記されていますが
時代が異なる????
平安時代末期から鎌倉時代の庭園は
先の平安時代の庭園と同じく
浄土式の池泉庭園でありながら、
初期の段階では池泉舟遊式であったものが、
後に回遊式となっていったとのことです。
広い池庭に蓬莱島や鶴島、
亀島などを配し、三尊石組の手法が
でてきたりという変化がでていったともあります。
そうした変化を遂げながら、
次の室町時代の庭園手法に
繫がっていったとされています。
平安時代の庭園は陸奥ならば
何と言っても毛越寺。
鎌倉時代の代表的な庭園としては
西芳寺庭園(通称”苔寺”)が挙げられます。
ちょっと想像してみると楽しいですね。
それなりの風流な暮らしを
なさっていたのでしょう。
<近くの史跡>
なお、この藤倉舘の東側には
源義経と恋仲になったという
皆鶴姫の碑と墓があります。
更に源義経が奥州へ逃れる際に、
馬(駒)を繋いだとされている
「駒繋石」があります。
(鏡山地区からの移転)
また時代は異なりますが
暦応5年(1342年)12月敬白と
観音菩薩の梵字が刻まれた
「暦応の碑」があります。
【所在地】
〒969-3463 福島県会津若松市河東町倉橋藤倉208
佐原義連と相模・佐原城、一ノ谷の合戦「鵯越の逆落とし」一番乗りの武勇で有名、会津・蘆名氏の祖です。
会津若松城(鶴ヶ城)~日本100名城、蘆名氏が築城、伊達・上杉・蒲生・加藤・保科・松平と続いた天下の名城。
猪苗代城 ~三浦一族で蘆名氏と同族の猪苗代氏が築城し約400年間支配、江戸時代は会津藩の重要拠点でした。
会津・北田城跡~三浦一族・佐原盛蓮の次男の佐原広盛が築城し、北田氏を名乗り7代続きました。
会津新宮城跡~三浦一族の佐原盛蓮の六男である新宮氏が築城、国の史跡です。
三浦義明と衣笠城合戦~長老は自らの命を盾に三浦一族の未来を守りました。
三浦義澄~源頼朝を支えた宿老の一人で13人の合議制のメンバーで相模守護。三浦一族の栄枯盛衰。
芦名城~戦国大名・蘆名氏の発祥の地であり、三浦一族の本拠地である衣笠城の支城でした。








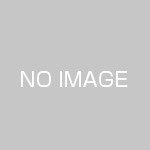







この記事へのコメントはありません。