【三瀬館】
三瀬館は伊勢国司・北畠具教の隠居所で、
北畠氏が滅亡する「三瀬の変」
の舞台になった場所として
知られています。

北畠具教は伊勢に侵攻した
織田信長と和睦を結ぶと、
最初は笠木館に退き、
さらに三瀬に館を築き隠居して、
大御所と呼ばれました。
けれども天正4年(1576年)に
織田信雄が差し向けた客により
謀殺されると、織田信長の命で
森清十郎が城主となりました。
現在跡地には階段状に
連続した九段ほどの削平地と、
石垣が一部残っています。

また付近には北畠具教公胴塚と
北畠神社があります。

<北畠具教公胴塚の碑>
子孫の方が江戸時代初期に建立したそうです。

【縄張形態】
居館
【築城主】
北畠具教
【築城年】
元亀2年(1571年)
【主な城主】
北畠具教、森清十郎
【遺構】
曲輪、石垣
【指定文化財】
県史跡
【交通アクセス】
(電車)
JR紀勢本線「三瀬谷」駅から徒歩約25~30分
JR紀勢本線「三瀬谷」駅からタクシーで約10分
(車)
紀勢自動車道「大宮大台」ICから11分
【所在地】
〒519-2403 三重県多気郡大台町上三瀬 大戸 地1012
北畠具教胴塚 ~三瀬館跡の谷を隔てた南側の小高い所にあります。
三瀬砦~北畠家の家臣である三瀬氏歴代の居城跡とされ、三瀬館を守護していました。
大河内城~大河内御所と呼ばれた北畠三御所の中でも代々の筆頭格で、 宗家が絶えた際には継ぐ立場でした。
田丸城~続日本100名城、南朝拠点として北畠親房、北畠顕信が築城、後に同一族の田丸氏が入城し織田信雄に明け渡しました。
織田信雄~織田信長の次男、散々な目に遭うも長生きしその血筋は明治維新まで受け継がれました。
笠木館~笠木御所とも呼ばれ北畠氏の一門である坂内氏の居館、県内屈指の中世の居館跡となります。
岩出城~北畠氏の一族である田丸直昌が築城、後に蒲生氏郷に従い、会津へ付き従いました。
木造城~北畠氏領域の最北端に位置し木造氏は北畠一族だが織田信長に従い北畠氏攻略の先駆けとなった。
安濃城~中世末期として県内最大級の丘陵城郭、築城は長野一族の細野氏、出自は工藤祐経の三男。



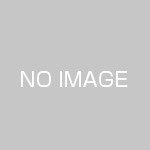












この記事へのコメントはありません。