【紀貫之邸跡】
高知県南国市立国府小学校の東300mの南側に
48代目の国司、紀貫之邸跡があります。
邸跡では高浜虚子の句碑等もあり、
この邸跡の南一帯は土佐の国衙(こくが)跡となっています。
【国衙】
国衙(こくが)は、
日本の律令制において国司が
地方政治を遂行した役所が置かれていた区画です。
国衙に勤務する官人・役人(国司)や、
国衙の領地(国衙領)を「国衙」と呼んだ例もあります。
<国府>
各令制国の中心地に国衙など
重要な施設を集めた都市域のこと。
<国衙>
またその中心となる政務機関の役所群を「国衙」といいます。
<国庁(政庁)>
さらにその中枢で国司が
儀式や政治を行う施設を国庁(政庁)と呼んでいました。
【古今集の庭】
紀貫之邸跡に隣接しています。
古今和歌集選者であった紀貫之にちなみ、
和歌32首をその草木に掲示し
「曲水の流れ」などを配した平安朝をテーマとした庭園です。
【所在地】
南国市比江
【電話】
088-880-6569(南国市生涯学習課)
【交通アクセス】
南国I.Cから南へ約2km、
JR四国・土讃線及び土佐くろしお鉄道のごめん・なはり線
「後免」駅より北へ約3km
国府小から東へ300m
【駐車場】
無料15台
<場所>
青印は無料駐車場の出入り口付近。
【紀貫之】
紀 貫之(き の つらゆき)は、
平安時代前期から中期にかけての貴族・歌人です。
下野守・紀本道の孫で紀望行の子です。
官位は従五位上・木工権頭、贈従二位。
「古今和歌集」の選者の一人で、三十六歌仙の一人です。
貞観8年(866年)または
貞観14年(872年) 頃の
生まれとされているそうです。
延喜5年(905年)、
醍醐天皇の命により
初の勅撰和歌集である「古今和歌集」を
紀友則・壬生忠岑・凡河内躬恒と共に撰上。
また、仮名による序文である仮名序を執筆しています。
「やまとうたは人の心を種として、
よろづの言の葉とぞなれりける」
で始まるこの仮名序は、
後代の文学に大きな影響を与えました。
また「小倉百人一首」にも和歌が収録されています。
理知的分析的歌風を特徴とし、
家集『貫之集』を自撰しています。
スポンサーリンク
【日本文学史上における最大の歌人として】
日本文学史上において、
少なくとも歌人として
最大の敬意を払われてきた人物でした。
種々の点でその実例が挙げられますが、
勅撰歌人として「古今和歌集」(101首)
以下の勅撰和歌集に435首の和歌作品が
入集しているのは歌人の中で最高数であり、
三代集時代の絶対的権威者であったといえるでしょう。
なお、散文作品として「土佐日記」があります。
【土佐日記】
「土佐日記」(とさにっき)とは、
平安時代に成立した日記文学のひとつです。
日本の日記文学で完本として
伝存するものとしては最古のものとなります。
紀貫之が土佐国から京に帰る最中に起きた出来事を
ジョークを交えて綴ったもので、
成立は承平5年(934年)頃といわれています。
古くは『土左日記』と表記されていたそうです。
【日本初の日記文学】
日本文学史上、
おそらく初めての日記文学と言われています。
紀行文に近い要素をもっており、
その後の仮名による表現、
特に女流文学の発達に
大きな影響を与えたとされています。
「蜻蛉日記」、「和泉式部日記」、「紫式部日記」、
「更級日記」などの作品にも
影響を及ぼした可能性は高いと見られています。
延長8年(930年)から
承平4年(934年)にかけての時期、
紀貫之は土佐国に国司として赴任していました。
その任期を終えて土佐から京へ帰る
紀貫之ら一行の55日間の旅路とおぼしき話を、
書き手を女性に仮託し、
ほとんどを仮名で日記風に綴った作品です。
57首の和歌を含む内容は様々ですが、
中心となるのは土佐国で亡くなった愛娘を思う心情、
そして行程の遅れによる帰京をはやる思いとのことです。
また、特筆すべき点は諧謔表現を多く用いていることです。
なお、諧謔表現とはジョーク、
駄洒落などといったユーモアの意味です。
成立の過程は不明となっています。
考えられている事項としては、
紀貫之はおそらく帰京の途上で漢文の日記をつけ、
土佐日記を執筆する際に、
それを参照したのではないかとのことです。
また、土佐日記は虚構を交えたものです。
明らかに実録の日記そのものではなく文学作品といえます。
【写本群】
「土佐日記」はある時期までは
紀貫之自筆のものが伝わっていたそうです。
鎌倉時代までは京都蓮華王院の宝蔵に
納められていたそうですが、
のちに歌人尭孝の手に渡り、
さらにそれが室町幕府の8代将軍である
足利義政に献上されてからは
足利将軍家の所蔵となっていたとのことです。
けれども、その後の消息については
絶えてしまっているとのことです。
写本としては、
自筆本から直接に藤原定家、藤原為家、
松木宗綱、三条西実隆らにより筆写され、
これら4系統の写本が伝わっているそうです。
中でも藤原定家本と藤原為家本は、
紀貫之自筆本の再構成として重要であるそうです。
細川藤孝(細川幽斎)~武道・文芸・芸術・コミュ能力と多才多芸な武将~巧みに世を渡り、運も引き寄せる
足摺岬~黒潮海流の接岸と地球が丸いことを実感できるミシュラン★★場所~駐車場や行き方など



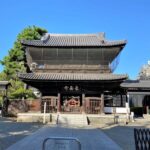













この記事へのコメントはありません。