【畠山重保】
畠山 重保(はたけやま しげやす、
生年不詳 – 元久2年6月22日(1205年7月10日))は、
鎌倉時代初期の武将です。
父は畠山重忠で母は北条時政の娘(政子、義時とは異母妹)です。
通称は六郎です。
【生涯】
兄に畠山重秀がいますが、
北条氏を母とする畠山重保が
嫡子の扱いを受けていたと見られています。
皇国地誌では、
現在の横浜市戸塚区汲沢町で
源氏山と呼ばれる小山付近の小字で
六郎丸にある陣屋跡が
畠山重保の居館であったという
古老の口伝を収録しています。
【畠山重忠の乱】
元久2年(1205年)6月22日早朝、
北条時政の後妻の牧の方の娘婿である
平賀朝雅との確執から、
謀反を企てたという疑いをかけられてしまい、
由比ガ浜に呼び出された所を、
北条時政の意を受けた
三浦義村によって討たれてしまいます。
畠山重保が殺されたことを知らずに
鎌倉へ向かっていた父である畠山重忠は、
北条義時率いる畠山重忠討伐軍に攻められて討死し、
平姓畠山氏は滅亡となったのでした。
【源氏系の畠山氏へ】
畠山重忠旧領と畠山の名跡は、
畠山重忠未亡人の北条時政の娘と、
足利義兼の庶長子である
足利義純が婚姻して継承されたということです。
なお、足利義純が婚姻した女性の異説として、
畠山重忠と北条時政の娘と間に生まれた
畠山重忠の娘、という説もあるとのことです。
【子孫】
子に時麿(小太郎重行)があったと伝え、
目黒氏を称したということです。
最も目黒氏の正確な出自は不詳であり、
畠山重保の子孫ではないとする説もあるそうです。
また畠山重保には、
父と同じ名の重忠と言う子がいたとも言われており、
こちらは浄法寺氏の祖となっているようです。
【墓塔】
由比ガ浜の畠山重保邸跡には
畠山重保の宝篋印塔があります。
【六郎さま】
畠山重保の宝篋印塔は「六郎さま」と呼ばれ、
咳で苦しむ人々が願をかけると、
咳の病が治ると云い伝えられています。
通称が「六郎」であった畠山重保自身が
喘息を持っていたということから
このようなお話が云い伝えられているとのことです。
スポンサーリンク
願のかけかたは、
竹の筒にお茶を注いで
これを宝篋印塔に供えて拝んだとのことで
墓の脇には「六郎茶屋」という
お茶屋さんもあったそうです。
・・・お茶屋さんが商売を始めるにあたって
広めたのかしら??
あらぬ疑いをかけられ、殺されてしまった
畠山重保の名が忘れ去られずに
後世に語り継がれていく、
という点ではよいかもしれませんね。
ところで鎌倉初期の時代も
「喘息」ってあったのですね。
願掛け方法としてお茶をかける、くらいですから
一般庶民が飲料としてお茶が浸透していたと思うので
この話は少なくとも江戸時代以降ですかね。
【鎌倉時代のお茶の文化】
お茶の文化自体は、鎌倉時代にあったようです。
日本の臨済宗(禅宗の一派)の開祖である
栄西(ようさい/えいさい、1141年⇒1215年)が
留学先の宋から、
禅院で飲茶が盛んに行われているのを見聞きし、
帰国後、日本初の茶の専門書「喫茶養生記」を著し、
お茶の効能を説いたそうです。
そして栄西は、深酒の癖のある将軍の源実朝に、
良薬としての茶にそえて、
本書を献上したと「吾妻鏡」に記されています。
その後、禅宗寺院に喫茶が広がると共に、
社交の道具として武士階級にも
喫茶が浸透していったそうです。
【将軍源実朝と畠山氏】
鎌倉幕府の御家人であった畠山重忠の末子として
畠山重慶(はたけやま ちょうけい)がいました。
畠山重忠の乱で父である畠山重忠と
兄の畠山重秀・重保ら一族は
北条氏率いる幕府軍によって滅ぼされ、
畠山氏の名跡は北条氏縁戚であった
足利義純が継承し、平姓畠山氏は断絶します。
畠山重慶は僧となり、
大夫阿闍梨重慶(たいふあじゃりちょうけい)となります。
乱の8年後の建保元年(1213年)9月19日、
日光山別当の法眼弁覚より、
幕府に「故畠山重忠の末子である
大夫阿闍梨重慶が、当山の麓に籠居して牢人を集め、
また祈祷を行っており、謀反を企てている」
という使者が送られます。
直ちに将軍源実朝の御前に報告され、
その場に祗候していた
長沼宗政に重慶を生け捕るように命が出されると、
宗政はその日のうちに
郎党9名を連れて下野国に出発しました。
7日後の26日、
下野国から鎌倉に戻った宗政は
重慶の首を斬って持参します。
それに対して将軍である源実朝は
「重忠は元々罪なくして誅殺された。
その末子の法師がたとえ陰謀をめぐらしたとしても、
命に従い、まずその身を生け捕りにして
陰謀の如何によって処分すべきであった」
と述べて嘆いたということです。
ま、「畠山重忠の乱」となるそのきっかけを
図らずもつくってしまったのは
源実朝ですし、ね。
【こじつけかもしれませんが・・・】
「お茶」「実朝」「畠山氏」という言葉を
つなげていくと「六郎さま」を広めた元祖が
実は源実朝の密やかな「仰せ」によるもの、
だったりして。
いえいえ、ほんの独り言です。
【所在地】
鎌倉市由比ガ浜2丁目1089番
明徳4年(1393年)(室町時代)
銘宝篋印塔(鎌倉市指定有形文化財)
また、横浜市金沢区釜利谷南1-5の
禅林寺の境外墓地にある五輪塔にも、
畠山重保が実はこの地に逃れて自刃したという伝承があり、
「伝畠山重保墓」として
横浜市登録地域文化財に登録されています。
「白山道六郎ヶ谷公園」の後ろにあります。
【お墓の所在地】
〒236-0045 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南1丁目4−22
【交通アクセス】
専用の駐車場はありません。
お墓前にある駐車場は月極の他の駐車場です。
近隣に「三井のリパーク・横浜市金沢区釜利谷南2丁目」があります。
最寄り駅:京急「金沢文庫」「金沢八景」
「金沢文庫」西口よりバス
(文10・11)⇒「白山道」下車5分。
(文7)⇒「パークタウン入口(バス)」下車8分。
「金沢八景」バス(船08)⇒「六浦」下車徒歩15分。
2022年NHK大河ドラマ
「鎌倉殿の13人」では
杉田 雷麟(すぎた らいる)さんが演じられています。
菅谷館跡と鶴ヶ峰・二俣川の古戦場散策~畠山重忠公の足跡を訪ねて。
北条時政~先見性を持ち才腕を振るって幕府の実権を掌握するが暴走して寂しく去る。
北条義時~鎌倉幕府2代執権~冷酷無情・現実を客観視して行動できる理想家なのか?
牧の方~北条時政を操り?陰謀を巡らせジャマな将軍や御家人たちを消したヤバすぎる人
平賀朝雅~源氏門葉の一族で妻は北条時政と牧の方の娘、故に権力争いの渦中に巻き込まれていきます。





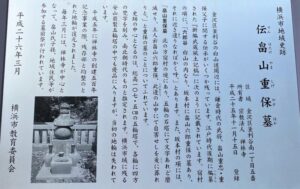
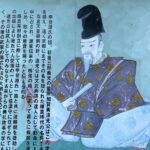







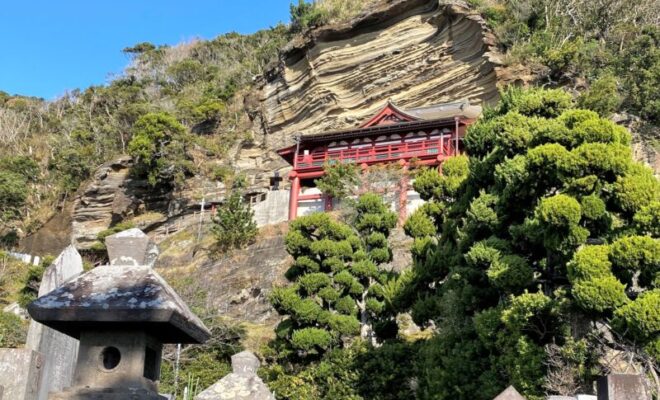





この記事へのコメントはありません。